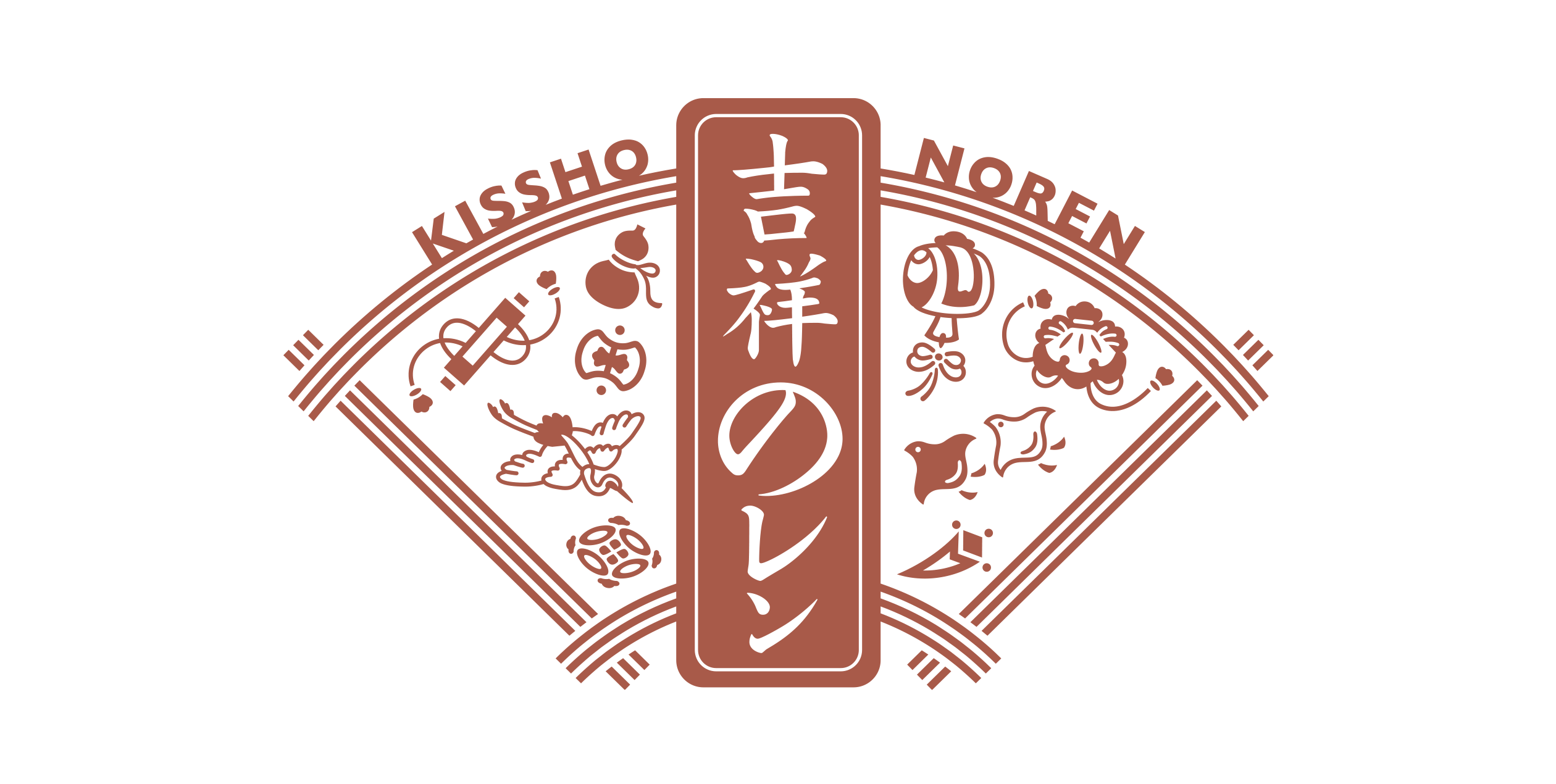『おにぎりとおむすび』

春爛漫。
遠足などの行楽で、また散歩の途中やお昼休みに
青空の下お弁当をいただくのも気持ちのいい季節です。
日本のお弁当は単に「持ち運ぶ食料」というだけではなく
栄養や彩を考えたり、「楽しむための食事」の要素も強く
世界でも「bento」とよばれ、注目される文化として発展しています。
お弁当の定番といえばおにぎり。
なんと
石川県の弥生時代の遺跡から蒸したご飯を手で握ったと思われるものが
炭化した状態で見つかっているそうですし
古事記にも「握飯(にぎりいい)」という言葉が出てくるとか。
おにぎりはずいぶん昔から作られてきたことが分かりますね。
にぎり飯を「おにぎり」と呼ぶ方、
また
「おむすび」と呼ぶ方、いらっしゃいますよね。
「おにぎり」の語源はご飯を握る動作からきているといわれます。
そして
「おにぎり」は「鬼を切る」に通ずるといわれ
【魔除け】のご利益があるとも考えられたとか。
民話の中には鬼に「おにぎり」を投げつけて退治する話もあるそうです。
一方
「おむすび」の語源は
農業の神である「神産巣日神(かみむすびのかみ)」に由来する、
という説があります。
「お結び」と表し【良縁をつなぐ】縁起を担ぐともいわれます。
長い間愛されている、おにぎりは美味しく楽しいだけでなく
ひとの想いも握られた縁起の良いものなんですね。